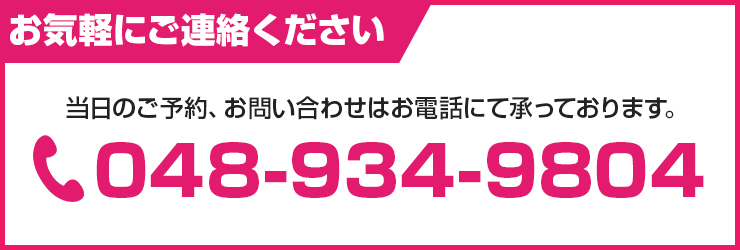【急患対応】お急ぎの方は048-934-9804まで!
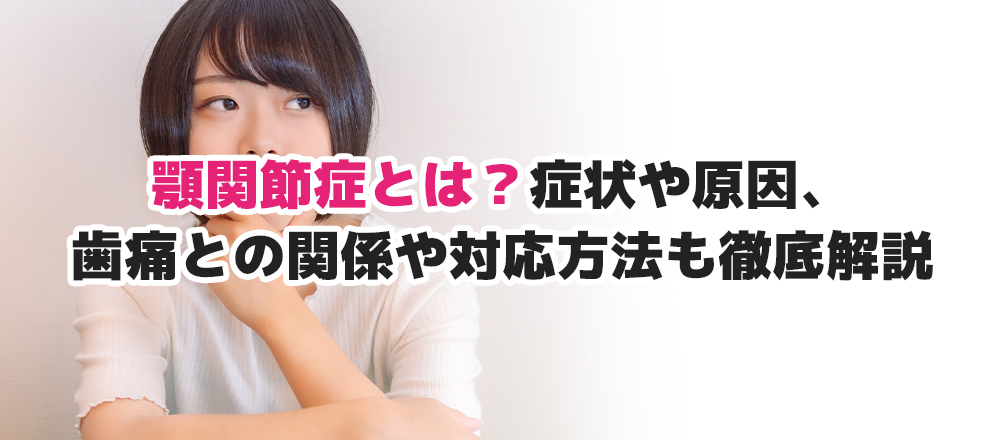
顎関節症といえば、顎の関節部や周りの筋肉の痛みをともなう病気として知られていますが、実は、顎の痛みだけでなく、歯の痛みを引き起こす場合もあります。
今回は、顎関節上の症状や原因を説明するとともに、歯痛との関係や対応方法も徹底解説します。
顎関節症とは?

顎関節症の症状は、実にさまざまですが、代表的な症状として以下の5つの主要な症状(特徴)があります。
- 上顎と下顎の関節部分や周りの筋肉の痛み
- 開口障害
- 顎関節付近の雑音
- 咀嚼筋の痛み
- 口を完全に閉じられない
これらの主要な症状が、慢性的につづいている状態にあることを総括的に顎関節症と呼んでいます。
主な症状が1つ、もしくは複数重なって発現することもあります。
顎関節症の症状とは?
顎関節症の代表的な5つの症状について詳しく説明します。
上顎と下顎の関節部分や周りの筋肉の痛み
顎関節やその周辺、こめかみあたりが痛みます。
食事中など顎を動かすことで痛むのが特徴です。
開口障害
人の口は、正常時に指を縦に3本分(約4~5cm)入る程度は開けられるとされています。顎関節症では、2本程度(約3㎝)以下しか、口が開かなくなります。
顎関節付近の雑音
顎を動かしたとき(稼働時)に、耳のあたりで、カクカクと関節の音がしたり、ミシミシ、ジャリジャリといった独特の雑音が生じます。
咀嚼筋の痛み
顎の動きが正常でなくなるため噛み合わせがずれ、物を噛んだときに筋肉に違和感を感じます。
口を完全に閉じられない
顎関節内の構造に異常が発生し、上下の歯列に隙間ができてしまいまい、完全に噛みしめることができず、口が閉じられなくなります。
顎関節症の原因とは?

従来、顎関節症の原因は「噛み合わせの異常」とされてきました。
しかし、現在は、それだけではなく、原因となる因子がほかにもあるという考えが一般的となっています。顎関節症の原因には、どのようなものが考えられるのでしょうか。
ブラキシズム
ブラキシズムとは、「歯ぎしり」や「くいしばり」などの総称です。
ブラキシズムは、筋肉を緊張させ、顎関節に大きな負荷をかけます。
ブラキシズムは、仕事やスポーツなど、何かに集中する際や、就寝中に無意識に発生する場合が多いです。
偏咀嚼
偏咀嚼とは、左右の歯のどちらか一方で噛むクセのことです。どちらか片方で咀嚼することで、顎関節に負担がかかり、顎関節症が発症します。
習癖
「習癖」とは、頬杖をつく、うつ伏せに寝るなど、顎の一部に過度に負担のかかるクセのことです。習癖により、顎に歪みが生じたり、関節に過度な負担がかかったりすることで顎関節症が発症します。
噛み合わせの不良
噛み合わせが悪い=顎関節症ではありませんが、偏咀嚼やブラキシズムと強く関連しているため、顎関節症に結びつく原因と考えられています。
ストレス
ストレスを感じることによる精神的な緊張により、ブラキシズムが発生することがあり、ストレスも顎関節症の原因のひとつとされています。
外因的要素
歯の治療の際に、大きく口を開けた場合や、顎周辺を打撲し関節や靭帯を損傷した場合などでも顎関節症になるケースがあります。
顎関節症を予防する生活習慣とは?
生活習慣を気をつけると顎関節症を予防することができます。
ぜひ、ここに挙げた要素に気をつけて生活してください。
歯が接触することを避ける
ブラキシズムを避けるために、できるだけ歯が接触することを避けるようにしましょう。
固いものを食べない
固いものを食べすぎると顎に負担がかかるので、あまり固いものを食べるのは控えましょう。
また、偏った場所で、硬いものを噛むのは厳禁です。
顎へ負担のかかる習癖をやめる
テーブルに頬杖をつく、うつ伏せ寝をするなどのクセはやめましょう。また、猫背も顎が前に突き出た状態になり、顎関節に歪みを生じさせる原因となります。
口を大きく開けすぎない
負荷が高い大口開きは控えましょう。
歯科治療等、やむを得ず大きく口を開けるような場合には、事前に、どの程度、開口すれば良いかを歯科医師に相談することをおすすめします。
適度なストレス解消を!
ストレスから無意識にブラキシズムを発症している場合もあります。
意識して、リラックスしてすごす時間をつくりましょう。
顎関節症で歯が痛む?
虫歯や親知らずがないにもかかわらず「奥歯の辺りが痛む」といった場合には、顎関節症による痛みが疑われます。
顎の周辺には、咀嚼筋とその他にも20以上の筋肉があります。
歯ぎしりや食いしばりが癖になっている人は、必要以上にこの咀嚼筋を使いすぎてしまっている状態にあります。
足や腕の筋肉と同様、顎の筋肉も、使いすぎれば筋肉痛が起こります。
つまり、咀嚼筋やそのほか顎の周辺の筋肉が筋肉痛になるくらいの力の負担を、歯や歯茎にもかけているということです。
その結果、歯や歯茎の周りの神経を刺激し、痛みを発生させます。
顎関節症が引き起こす全身の症状は?
顎関節症を慢性的に抱えていることで起こるとされている全身的な症状がいくつかあります。
代表的なものは以下の通りです。
- 頭痛
- 肩こり、首こり
- めまい、耳鳴り
- 不眠症、睡眠障害
- しびれ
- 飲み込むときの違和感
- 自律神経失調症、うつ病
これら以外にも、妙にまぶしく感じる、口が渇くなどを感じる方もいます。
もし、顎関節症の症状が落ち着いているのに、全身症状がつづいている場合は、別の病気の可能性もあるので、早めに医療機関を受診しましょう。
顎関節症の治療はどこでするべき?
顎関節症の歯の痛み、歯の周辺組織の痛みで苦しんでいる方の多くが、治療する場合には歯科医院を受診されますが、顎関節症に詳しい歯科医院でない場合は、適切な治療を受けられないケースも多々あります。
顎関節症が疑われる場合には、まずは、東武伊勢崎線・谷塚駅から徒歩1分の場所にあるハーツデンタルクリニック谷塚駅前に、気軽にご相談ください。丁寧なカウンセリングをして、痛みの原因を特定し、適切な治療をご提案いたします。
顎関節症と類似の症状の病気は?
顎関節症の全身症状と類似の症状を発症するのが「帯状疱疹」です。
主に「頭痛」「耳鳴り」があり、耳の後ろに水疱ができ、首元に違和感を感じます。
帯状疱疹の場合、慢性的な拍動頭痛というよりも、刺すような激しい頭痛がつづきます。重症化すると、顔面麻痺が出る場合もあります。
帯状疱疹が疑われるときは、歯科医院ではなく内科、脳神経外科などを受診しましょう。
まとめ
顎関節症は、顎の症状とさまざまな全身症状を引き起こす場合があり、歯痛にも関係しています。
顎関節症にともなう悩みや不安が生じたならば、東武伊勢崎線・谷塚駅から徒歩1分の場所にあるハーツデンタルクリニック谷塚駅前にご連絡ください。
もちろん、必要があれば、歯科医師が適切な受診科を紹介いたします。
ハーツデンタルクリニック谷塚駅前には、谷塚、谷塚町、谷塚上町、瀬崎や東京都足立区花畑などのエリアから多くの患者さんが来院されています。
顎関節症は、決して自己判断で放置せず、信頼できる歯科医師を受診することをおすすめします。

ハーツデンタルクリニック西白井駅前の院長。城西歯科大学(現 明海大学)卒業。仕事でうれしい時は思うような治療ができ、患者様に喜ばれ、お礼を言われたとき。
ハーツデンタルクリニック西白井駅前