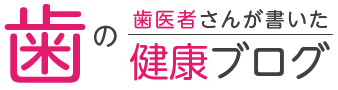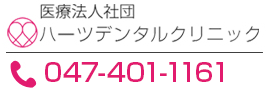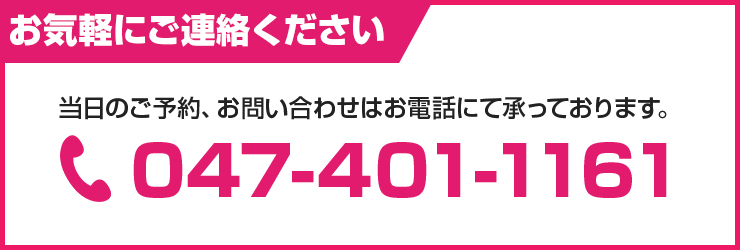「親知らずの抜歯は難しい」という言葉をよく耳にしますが、普通の抜歯の手順と違いがあるのでしょうか。また、親知らずの抜歯の過程で起こりうるリスクには、どのようなものがあるのでしょうか。
今回は、親知らずの抜歯を検討されている方の疑問や不安が少しでも解消されるよう、親知らずの抜歯の事前準備や抜歯の手順、抜歯におけるリスクについてご紹介します。また、親知らずを抜かないリスクや「親知らずの抜歯がこわい」と思われている方へ恐怖心なく抜歯ができる方法についてもご説明しますので、ぜひ、参考になさってください。
親知らずの抜歯の準備は?
親知らずの抜歯は、親知らずの生え方によって、その抜歯の難易度が大きく変わります。そこで、親知らずの抜歯の際には、次に挙げるような準備を行います。
どのような抜歯になるのかを精査する
親知らずの生え方は主に、「他の歯と同じようにまっすぐ生えている場合」、「斜めに生えている場合」、「完全に埋没し歯ぐきの中で近隣の歯に障害を与えている場合」の大きく3つのパターンに分かれます。
3つのパターンのそれぞれで、抜歯の方法や時間、術後の予後も違います。そのため、事前に歯科医師と患者間で抜歯の手順などを十分に確認し合い、双方で合意した後に抜歯が行われるようにします。
歯周病がないかの確認
歯周病が進行している場合は、抜歯後の予後不良につながるため、事前にクリーニング(歯石除去等)を行います。膿が溜まっていれば治療を行い、歯周組織の状態が落ち着いてから抜歯をします。
予後を考慮して予約をする
前述したとおり、親知らずは生え方によっては、抜歯が非常に難しくなる場合があります。通常は局所麻酔で抜歯を行いますが、抜歯が難しい場合は、入院をして全身麻酔下で行うこともあります。また、傷口が大きくなったときは、通常の抜歯よりも治るまでに時間もかかります。
抜歯の予約を入れる際には、近々旅行の予定がないか、大切な仕事と重なっていないかなどを確認しておきましょう。
親知らずの抜歯の手順
親知らずの抜歯の手順は、生え方によって異なります。それも踏まえて、親知らずの抜歯の手順について説明します。
歯ぐきの表面に麻酔を行う
最初に、局所麻酔注射の痛みを和らげるため、歯ぐきの刺入点に表面麻酔の塗り薬を塗布し、1~2分おいておきます。
局所麻酔を行う
局所麻酔の方法は、親知らず周辺の歯ぐきに注射をする方法と、親知らずの奥のほうにある太い神経に注射をする方法があります。また、抜歯が難しい場所などの場合には、全身麻酔を使用する場合もあります。
歯ぐきを切開(完全に埋伏している歯の場合)
完全に埋伏している親知らずを抜歯する場合には、メスで親知らずの上部の歯ぐきを切開して歯を露出させます。
歯槽骨切削(顎の骨が邪魔している場合)
親知らずがある位置が深かったり、斜めに生えて顎の骨が邪魔して抜歯ができない場合には、周辺の歯を支える骨である「歯槽骨」を削ります。
歯の分割(歯の頭部分が抜歯の道具に引っかからない場合)
歯が横を向いていたり、斜めに生えて歯の頭の部分が隠れていたりなどして抜歯鉗子(歯を抜くペンチのような道具)が歯をつかめない場合には、抜歯鉗子が歯をつかめるよう、親知らずをいったん分割します。
抜歯
抜歯ができる状態になったら、普通の歯と同じように、抜歯鉗子を使って歯を抜きます。
抜歯窩の消毒
抜歯後、歯ぐきに開いた穴に残りカスなどが無いように精製水等で洗浄します。
レントゲン撮影
抜歯後、歯の破片や割れた根っこが残っていないか、レントゲン撮影で確認します。
縫合
抜歯窩を縫合します。歯ぐきを切開した場合は、元の位置に戻して縫合します。
抜歯後の説明と投薬
歯科医師から、抜歯当日のすごし方や日常生活での注意点などの指導を受けます。細菌感染防止のための抗生剤や痛み止めなどが処方されます。
抜糸
抜歯窩の治り具合を確認するため、通常は、術後1週間~10日後に歯科医院で診療を受けます。その際、傷の回復が順調であれば抜糸します。
親知らず抜歯に潜むリスク
親知らずの抜歯は通常の抜歯よりも難しく、歯科医師も神経を使うほどの外科治療です。親知らずの抜歯の過程や術後においては、どのようなリスクがあるのでしょうか。
切開しすぎると麻痺が残る可能性もある
歯肉切開の際、内側に深く切開しすぎると舌神経を傷つけてしまう危険性があり、舌神経が傷つくと術後に麻痺が出る可能性もあります。歯科医師は、切開をする際には細心の注意をしながら抜歯を行わなければなりません。
術後の痛みや腫れ
抜歯後にレントゲン撮影をして確認を行うことを怠ると、歯の残骸が残ったまま縫合してしまうることにもなります。痛みや腫れの原因になる場合もあるため、歯科医師は術後に必ずレントゲンで確認しなければなりません。親知らずを抜くときは歯ぐきと切ったり、骨を削ったりしますので、腫れる可能性があります。術後2日目くらいが腫れのピークとなり、1週間ほどで腫れは治ります。
腫れと同様に外科手術に痛みはつきものです。ただ、基本的には鎮痛剤で抑えることが可能です。
内出血(皮下出血斑)
骨を大きく削った場合には、普段からアザができやすい方においては内出血でアザができることもあります。時間とともにアザは消えていきますが、1週間以上かかる場合もあります。
親知らずを抜かないリスク
親知らずは、どうしても抜かなければならないのでしょうか。抜かないことで起こりうるリスクには、次のようなものがあります。
歯ぐきが腫れる
親知らずのまわりの歯ぐきが、腫れる場合があります。特に完全に生えきっていなかったり、斜めに生えていたりする親知らずでは、腫れてしまうリスクが高くなります。
むし歯になりやすい
親知らず自体がむし歯になることもありますが、親知らずのひとつ手前の奥歯である第2大臼歯がむし歯になってしまったときには、治療が困難なケースもあります。
妊娠中のトラブル
妊娠中はホルモンのバランスにより歯ぐきが腫れやすい状態になります。親知らずを抜いていないと、妊娠中に親知らずのまわりの歯ぐきが腫れることがよくあります。質と鎮痛薬で対応します。
親知らずの抜歯がこわい方には静脈内鎮静法がおすすめ
親知らずの抜歯は、歯を削ったり、歯を砕いたりする場合もあるため「こわい」と思われる方が多くいらっしゃいます。こわくて親知らずの抜歯に踏み切れない方には、静脈内鎮静法(点滴麻酔)をおすすめします。
静脈内鎮静法とは静脈に鎮静剤を点滴する方法で、鎮静剤が効いてくると浅く麻酔がかかったようになり、難しい抜歯等の外科治療でも半分眠っているようなウトウトとした状態で、ほとんど痛みを感じずに受けることができます。
西白井駅から徒歩1分のところにあるハーツデンタルクリニック西白井駅前は静脈内鎮静法の多くの実績があります。静脈内鎮静法を検討されている方は、ぜひ、ご相談ください。
まとめ
親知らずの抜歯は、通常の抜歯とくらべて難易度が高いケースが多いため、歯科医師も事前準備や予後の確認に慎重になります。歯科医院側のスタッフも、受ける側の患者も、双方がしっかり手順やリスクを確認して臨むようにしましょう。
西白井駅から徒歩1分のところにあるハーツデンタルクリニック西白井駅前では、親知らずの抜歯に際しては、丁寧なカウンセリングを行いますので安心です。また、歯科治療に強い恐怖心をお持ちの方には、静脈内鎮静法をご提案しています。どうぞ、お気軽にご相談ください。

ハーツデンタルクリニック西白井駅前

ハーツデンタルクリニック八千代中央駅前

ハーツデンタルクリニック谷塚駅前